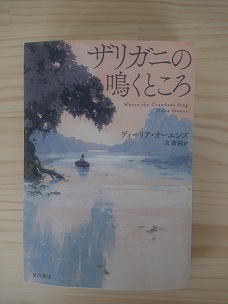
私にとって久しぶりの米文学。
2019年にアメリカで一番売れた本とのキャッチフレーズには何の魅力も感じなかったが、「もうひとつの主人公は湿地の生き物です」との書評に動かされて手に取った。
1950年代の南部ノースカロライナ州。まだまだ黒人への人種差別が歴然とあるが、白人の間にも格差社会のアメリカではホワイトトラッシュと呼ばれる最下層の人々がいた。ここで私は宮本輝の「泥の河」を思い出した。
主人公カイアはものごごろ着いた時から、暴力をふるう父親とそれにおびえる家族とともに湿地の掘立小屋に住んでいた。それでも、やさしい母親と兄ジョディがいたときはまだよかった。ある日、母が出ていき、そして兄が出て行って父親と二人きりになる。幼いながら、この父親とどううまくやっていくか、工夫をして、一時は平穏な生活もあったのだが・・・・
最後、湿地にひとり取り残されたカイア。読み書きも、お釣りの計算もできない。一度だけ学校へ行ってみるが、無残に傷つけられただけでまた湿地に引きこもる。味方は船着き場で燃料店を営む黒人のジャンピンとその妻のメイベルだけ。父が残したおんぼろボートで移動し、貝を掘って僅かな現金を得る生活。それでも、湿地にいるたくさんの鳥たちは友達でその羽根は宝物。
思春期にさしかかったカイアの前にジョディの友人だったテイトが現れる。彼は、カイトを同じように自然をそして生物を愛おしむ仲間として接し、彼女に読み書きを教えるが、そこで、彼女の能力に驚かされる。
ある日、この田舎町に不審死事件が起こる。転落死したのは、カイトと付き合っていたチェイスだった。
カイトの成長物語、カイトとテイトの恋愛青春小説、不審死のミステリー、そしてその裁判小説
いくつもの要素を持つこの小説だが、たくさんの生物、そして生物の生態が随所に散りばめられ、それこそがこの小説の大きな魅力になっている。経済第一主義ではジメジメして厄介な、開発すべき場所でしかない湿地が、実は多くの生物の楽園であることを静かに謳っている。
カイトの晩年には、この湿地にも開発の影が感じられるが、カーソン女史の「沈黙の春」が出版されたのはこのころだっただろうか。色々思うことは多い。
題名のザリガニの鳴くところとは生き物が自然のままに生きる場所のこと。作者は生物学者でもあり、そのことを遺憾なく発揮した魅力ある小説だった。
