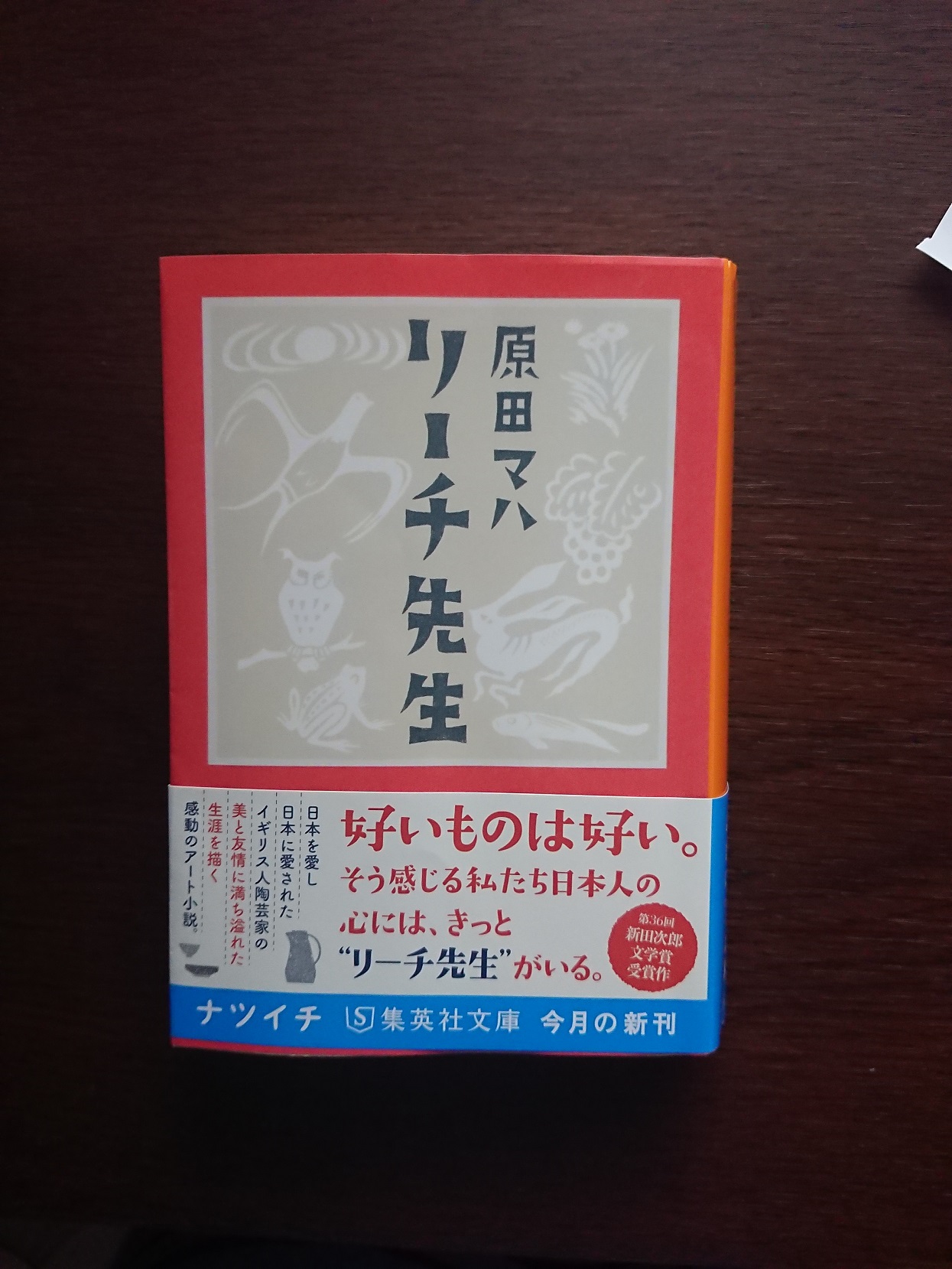
いつまでも元気だと思っていた高齢の母親が、急にひとりでの生活ができなくなり、私のそばでに来てもらうことになった。その為、様々な手続き、施設探し、受診の手助け、家事、そして古家の片付けと、とにかく毎日が精一杯でへとへと。
医療、介護については少しはわかっているはずの私でこれなのだから、一般の人々の苦労はさぞやと思われるし、行く先々で対応に当たってくれる人の専門知識、アドバイス、そして親身になった対応に本当に助けられた。
というわけで、この2か月は読書とは縁遠い生活だったが、ひと段落して立ち寄った本屋で見つけた大好きな原田マハさんの小説。そういえば延岡にいる友人も勧めてくれていたことを思い出して買って帰り、3日間で読んでしまった。
マハさん得意の美術にまつわるものだが、今回は陶芸家バーナード・リーチの物語。
冒頭、私たちにとっては身近な小鹿田の窯元から始まる。
昭和30年代、半農半陶で生活雑器を代々作っている里にイギリス人の高名な陶芸家バーナード・リーチがしばらく滞在するという知らせが来て、彼のお世話係をまだ見習いの沖高市がすることになった。初めて会うバーナード・リーチは途轍もなく背が高く、でも陶工の手を持った優しい大きな人物で、高市はリーチ先生と慕うのだが
「君のお父さんは、オキ・カメノスケ、という名前ではありませんか」
高市は、一瞬、息を止めて、リーチを見返した。なかなか言葉が出てこなかった。
沖亀之助―それは、まさしく高市の父の名前だった。
「ど・・・・・どうして、知っちょるとですか・・・・」
震える声で、高市は訊き返した。リーチの瞳に親しみの色が溢れた。
「やっぱり」リーチは懐かしそうに言った。情感のこもった、あたたかな声で。
「やっぱり、君はカメちゃんの息子でしたか」
リーチと高市は、互いに炎を映した瞳で見つめ合った。
パチパチと薪のはぜる心地よい音が漆黒の闇の中に響いていた。
このプロローグから一転、明治40年代に遡る。
両親を亡くし、横浜の食堂に引き取られて給仕をしていた14歳の沖亀之助は、留学前に立ち寄った高村光太郎から
「もし、君がこの先、英語を勉強したいとか、芸術を学びたいとか、本気で思っているのだったら、僕の家を訪ねてみたまえ」
と紙片を渡される。思いもかけない誘いに、16歳になった亀之助は、思い切って高村光雲の家を訪ねて書生として住み込むことになる。そこに、ロンドンで光太郎から受け取った紙片を握りしめて22歳のバーナード・リーチが訪ねて来る。
まだ、何者でもないリーチは、光太郎の語る日本にあこがれて、「日本と西洋、双方の芸術を理解し、高め合おうとする人物の到来が必要なんだ」の一言で日本行きを決意したのだった。
亀之助は初めはリーチの通訳として、その後はリーチを先生と仰ぎ、助手として行動を共にする。
それから紆余曲折があり、彼が生涯をかける陶芸と出会うわけだが、あの時代の芸術家たちが次々登場して、彼に絡んでくる。光雲、光太郎、志賀直哉、武者小路実篤、富本憲吉、そして最大のパトロンとなった柳宗悦。そして、濱田庄司、河井寛次郎まで登場する。
亀之助の目に映るこの時代の芸術家たちが眩しい。そして、読者である私も新たな美の創造にわくわくしながらも、亀之助の成長を見ていくことになる。登場する綺羅星のごとき芸術家に交じって、まったく知らない沖亀之助がバーナード・リーチのそばに、濱田庄司と共にいるわけで、まんまと作者の仕掛けにはまってしまった。
土と炎に格闘しながら、作陶していくリーチと亀之助。渡英した彼らが土を探し当てたときの喜び。亀之助の恋愛。そして、遠くに聞こえる戦争の足音。
エピローグでは成長した高市の登場となるわけだが、その結末は・・・
お茶を嗜む私には、やきものはとても身近なもので、茶碗や水指、香合などの茶陶。「用の美」という言葉で日常遣いの陶器の価値に光をあてた柳宗悦。そして、芸術として高めた濱田庄司やバーナード・リーチ。こんな、たくさんの「好いものは好い」そう感じるやきものに囲まれて暮らす幸せを改めて感じさせてくれた一冊だった。
